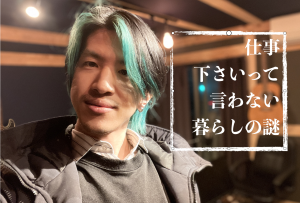お雑煮に見られる家系のルーツ

お正月からドリームシアターの真っ黒な譜面のネタでは息切れしてしまいますからね、お雑煮でも食べましょう。
我が実家でのお雑煮は、毎年必ずこれです!鰤!!ブリ!!
そう鰤のお雑煮です。そして、茹でた丸餅。
つきたてのものを出雲から送ってもらっているのですがこれがンマイ。
焼いても良いがやはり茹でたのがンマイ。のです。
- 鰤は、塩漬けしたものを水洗いして、茹でて出汁を取るのだとか。
- そこに、お酒で戻した十六島海苔(←読めまい、)うっぷるい のり と読みます。
- 島根県は出雲市の、十六島(うっぷるい)って島の岩肌にこびりついてるやつで、ちょっとしか獲れないので希少性が高いそうです。(風土記にも出てくる海苔で、日本で最も古い海苔とも言われています)
- そして、牛蒡、お豆腐が入っています。
- おつゆは、しょう油ベースです。
小さい時から当たり前のようにこれだったので他を知らないのですが、お雑煮って地域や家庭によって本当にそれぞれ様々ですよね!
まず●丸餅か
角餅か煮るのか 焼くのか?
小豆系なのか、白味噌系なのか、すまし汁系なのか?
お雑煮文化圏マップというやつがあってざっくり、西は丸餅、東は角餅…とか傾向が分かるようですね。
なんせ、お雑煮によってルーツが見えてくるというのも面白いものです!
うちは、母方の故郷が島根県は出雲で、十六島海苔(←だから読めない)なんかはまさに出雲ならでは、丸餅を茹でるのも出雲のお餅の特徴なんだそうな。
けど、鰤!これは、実は出雲ではなく、今は亡きお婆ちゃんの故郷である岡山のお雑煮に入れられていたのだそうです。それが出雲にきて、出雲の要素と結びついて、独特の鰤と十六島海苔のお雑煮になったと。
そしてそれが今うちで食べ継がれているというわけだ!!
こう考えるとなんとなく食べていたお雑煮にも家系のルーツの歴史を感じて感慨深いものがあります。
あなたのとこのお雑煮は、一体どんなの??
おわり。